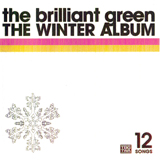 |
1.
|
intro -THE WINTER ALBUM- |
|
2.
|
Holidays! |
|
3.
|
Flowers |
|
4.
|
I'M SO SORRY BABY(album mix) |
|
5.
|
Forever to me ~終わりなき悲しみ~(album mix) |
|
6.
|
That boy waits for me |
|
7.
|
The night has pleasant time |
|
8.
|
Day after day |
|
9.
|
Rainy days never stays(album mix) |
|
10.
|
I'M JUS' LOVIN' YOU(album mix) |
|
11.
|
Running so high |
|
12.
|
escape |